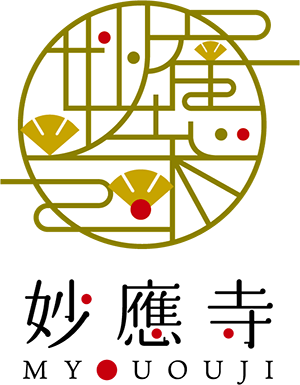御供養
どなたかが亡くなると、葬儀という供養を行います。
供養とは亡くなった方や仏様に供物をお供えし、手を合わせ、ご冥福を祈り、
感謝の気持ちに思いを馳せることです。
年に1度の故人の命日や、春・秋のお彼岸、お盆には仏様とご縁を結ぶ「読経作法」を差し上げます。
四十九日の頃には満中陰、お亡くなりになられて丸1年過ぎる頃には一周忌、
丸2年過ぎる頃には三回忌などの法事を行わせていただきます。
ご家族など、身近な人の死に関わる場合、不安を感じる方も多いでしょう。
ご葬儀やご供養の際は、前もってご連絡をいただくことで
さまざなご相談内容に対し、わかりやすくご説明したうえで供養を執り行わせていただきます。
ぜひご連絡ださい。
当寺院で行う御供養
-
葬儀
ご葬儀やご供養の際は、前もって妙應寺にご連絡ください。転勤などで引越してきたため供養をしてくれるお寺がいなくて困っている、など檀家以外の方もどうぞご連絡ください。葬儀では、一般的な葬儀の他に、水子供養など、ご家族の方がお望みになるスタイルに合わせて葬儀を執り行います。ご不明点や費用面についてもどうぞご相談ください。
-

-
法事
故人がお亡くなりになられてから数えて七日目の「初七日」、以降、七日ごとに区切って二七日、三七日……と続き、四九日を迎える頃「満中陰」の法要を行います。その後も、百箇日や初盆、一周忌、三回忌と続いていきます。仏様がお若いうちのご供養はとても大切で、それぞれの回忌には意味があります。法事では回忌のたびにさまざまな仏様と仏縁を結ぶための作法や読経をいたします。
-

-
水子供養
水子供養 とは、さまざまな事情によりこの世に生まれて来られなかった子どもの冥福を願い、供養を行うことです。生まれることができなくても、一つの大切な命です。
妙應寺では、お経を読誦し、お題目をお唱えし、水子の霊位を丁寧に供養いたします。 -

-
先祖供養
自身の存在は、自分を生んでくれた父母があり、先祖の存在があるということです。自分自身の存在のルーツへの感謝の想いを忘れず、現代人が失いつつある心の根源を再発見する手段の一つとして、「ご先祖供養」があります。
-

-
初七日
(しょなぬか)
-
二七日
(ふたなぬか)
-
三七日
(みなぬか)
-
四七日
(よなぬか)
-
五七日
(いつなぬか)
-
六七日
(むなぬか)
-
満中陰
七七日
四十九日(まんちゅういん・しちしちにち)
-
百箇日
(ひゃっかにち)
-
一周忌
(いっしゅうき)
-
三回忌
(さんかいき)
-
七回忌
(しちかいき)
-
十三回忌
(じゅうさんかいき)
-
十七回忌
(じゅうしちかいき)
-
二十三回忌
(にじゅうさんかいき)
-
二十五回忌
(にじゅうごかいき)
-
二十七回忌
(にじゅうしちかいき)
-
三十三回忌
(さんじゅうさんかいき)
-
三十七回忌
(さんじゅうしちかいき)
-
五十回忌
(ごじゅっかいき)
-
百回忌
(ひゃくかいき)
これより先五十年ずつ増える
その他、さまざまなご供養に対応いたします。お気軽にご相談ください。
-
仏壇
仏壇は、仏様やお亡くなりになった方々を祀る場所です。仏壇に向かって毎日手を合わせることもご供養です。ご命日やお彼岸、お盆には皆さまのお宅にお伺いさせていただき、仏壇の前でお参りをさせていただきます。仏壇を新しくされた際は開眼(魂入れ)という儀式を行います。仏壇が老朽化してしまった場合は「洗い」といって、仏具屋で金箔を貼り替えたり、金具を取り替えたりしてもらうことが必要となります。仏壇を入れ替えるときやお引越し、洗いの前に閉眼(魂抜き)を行い、中の仏様に一時的にお戻りいただきます。入替えや引越が終わった際は、再び開眼(魂入れ)のお勤めをさせていただきます。
-

-
お墓
仏壇が魂の休まる場所であるのに対して、お墓は無くなった方の身体が休まる場所です。お墓を移転する際や修復される際は閉眼供養、お墓をつくる際や移転後は開眼供養をいたします。
長年にわたってお祀りされてきたご先祖のお墓じまいをお考えの方は別途ご相談ください。 -